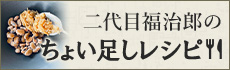極旨丹波黒納豆・一粒発酵
納豆の究極の旨味を追求してきた、二代目福治郎の逸品。
極旨(きわみ)
丹波黒豆納豆・一粒発酵
納豆の旨味は、どこまで高みへ行けるのか。
その問いに二十数年向き合い続けてきた職人が、ようやく辿り着いた答えです。

納豆の旨味の最高峰を目指して生まれた、二代目福治郎の最高傑作。
二代目福治郎・納豆づくりの原点

馬蹄職人から納豆職人へ、人生をかけた挑戦
昭和三十四年に、初代・福治郎が始めた小さな納豆屋「ふく屋」
「ただ、美味い納豆で喜んでもらいたい」——
その想いだけを胸に、家族の手で続けてきた商いです。
その原点は、今も二代目へ、そして三代目へと受け継がれています。
「納豆屋には絶対になりたくない」——そこから始まった物語

「どうせやるなら、日本一の納豆をつくる。」その決意から物語が始まりました。
私は1966年、秋田の小さな納豆屋の長男として生まれました。
子どものころのあだ名は、皮肉にも「なっとうや」。ところが当の本人は、納豆が大嫌いでした。
匂いも、粘りも、あの独特の存在感も苦手で、
「大きくなったら絶対に納豆屋にはならない」と本気で思っていた少年でした。
高校を卒業すると、憧れの大都会・東京へ。
バブル景気の真っ只中、スーツを着て、ビジネスマンとして一旗あげようと意気込んでいました。
ところが、バブルは崩壊。
前を向いて進んでいたはずの道は、突然目の前で途切れてしまいました。
そんなある日、テレビからこんな言葉が耳に飛び込んできます。
「納豆は、科学的に見てもものすごく健康に良い」——。
その瞬間、胸の奥で何かがひっくり返りました。
「納豆屋は、人の健康を支える仕事なんだ」
そう気づいたとき、私は家業を継ぐ決意を固めたのです。
そして、心の中でそっと誓いました。
「どうせやるなら、日本一の納豆をつくる。」
この一粒発酵 丹波黒豆納豆・極旨(きわみ)は、その誓いの延長線上にあります。
丹波黒——黒豆の王様。その潜在能力と、“皮と実”が教えてくれたこと

丹波黒の「皮」と「実」。その浸透圧の違いを知りつくした者だけが扱える豆です。
究極の納豆をつくるなら、まずは豆から。
そう考えた私は、日本中の大豆を探し歩き、その中で一つの答えに辿りつきます。
それが、黒豆の王様と呼ばれる丹波黒大豆です。
ふっくらと大きく、上品な甘みと香ばしい香り。お正月の煮豆としても知られる特別な豆です。
しかし丹波黒には、大きな「難しさ」もありました。
——皮と実の浸透圧が大きく違う。
皮は水を吸うのが遅く、実は水を吸うのが早い。
そのまま水に漬けてしまうと、実だけが先に膨らみ、皮が耐えきれずに破れてしまいます。
皮が破れるということは、その裂け目から、せっかくの旨味が水の中へ流れ出てしまうということ。
つまり、ただ黒豆を水に漬けて煮るだけでは、「本当の丹波黒の旨味」は引き出せないのです。
そこで私たちは、丹波黒と向き合い続ける中で、
「皮と実の吸水スピードを揃える」独自の水戻しの技術 を磨いていきました。
低温倉庫から出した豆をすぐ水に漬けるのではなく、
じっくり2日間かけて常温に戻してから、ようやく吸水を始める——。
たかが水漬け、されど水漬け。
大切なのは、豆の声を聞き、豆の性格を知ることなのです。
究極の旨味に辿りつくために、必要だったのは“一粒発酵”だった。

ひと粒ひと粒に向き合う、一粒発酵という常識外れの製法。
丹波黒のポテンシャルを最大限に引き出すには、従来の納豆づくりでは届かない——。
私たちは、早い段階でその「限界」に気づいていました。
丹波黒は大粒で、一粒ごとに大きさも、水分量も、皮の厚みも、甘みも違います。
その個性は魅力であり、同時に難しさでもあります。
通常の納豆のように、豆をひとかたまりにして発酵させてしまうと、
発酵の熱と湿度は「全体」に広がり、結果としてそれぞれの豆が持つ“最高の瞬間”が平均化されてしまうのです。
では、どうすれば丹波黒のひと粒ひと粒を「いちばん美味しい状態」に導けるのか。
私たちが出した答えは、シンプルで、そして常識外れなものでした。
——一粒ずつ、別々に発酵させてしまえばいい。
ひと粒ごとの水分、ひと粒ごとの火の通り方、ひと粒ごとの菌の付き方。
これらを、すべて“一粒単位”で整えていく。
圧倒的な手間と時間がかかることはわかっていました。
それでも、「究極の旨味」に辿りつくためには、この道しかないと確信していました。
2年8カ月の失敗。そして見つけた“発酵の黄金点 51.2℃”。

51.2℃という、丹波黒がもっともおいしくなる“発酵の黄金点”。
一粒発酵は、想像していた以上に困難な道でした。
温度を変えれば旨味が死に、湿度を変えれば香りが消える。
工場に泊まり込み、何十回、何百回と試作を繰り返しました。
その間にできあがったのは、納豆になりきれない黒豆や、香りの弱い失敗作ばかり。
同業者からは笑われました。
「そんなもの、無理に決まっている」
「そこまでして納豆を作る意味があるのか」
それでも諦めませんでした。
いつか必ず、「これだ」と言える一粒に出会えると信じていたからです。
そしてある日、ついにその瞬間が訪れます。
丹波黒ならではの甘みと香ばしさ、納豆らしい発酵の香り、なめらかな舌ざわり。
すべてが高い次元で調和した、一粒。
そのときの発酵温度が、51.2℃でした。
10時間かけて51.2℃まで上げ、そこから1時間だけ、その状態を保つ。
それ以上でも、それ以下でもダメ。
この「51.2℃で1時間キープ」という一点だけが、丹波黒の旨味を最高に引き出す黄金点だったのです。
こうして、極旨(きわみ) 丹波黒豆納豆・一粒発酵は、ようやく完成しました。
25粒、わずか3%の特大丹波黒だけ——極旨にふさわしい豆とは。

たった25粒。丹波黒の中の、さらに3%だけがここに並びます。
極旨で使用するのは、丹波黒大豆の中でも、さらに厳選されたごく一部の特大粒です。
摘心栽培で育てられた丹波黒大豆の中から、
粒の大きさ、形、表面の状態、色ツヤを一粒ずつ確認し、
わずか3%ほどの5ミリ以上の特大サイズだけを選び抜きます。
熱々の煮豆が冷めないうちに、隣同士で擦れないようにひと粒ずつ納豆菌を付着させ、
さらにそこから特大粒だけを拾い上げ、25マスの升形容器にひと粒ずつ静かに乗せていく——。
煮豆の温度が落ちてしまう前に行わなければならないため、
一度に作れるのは10個が限界です。
こうして選び抜かれた25粒は、まさに丹波黒の「代表選手」。
丹波黒のポテンシャルを、一皿の中に凝縮した姿が、この極旨なのです。
極旨を味わい尽くす、たったひとつの食べ方。
極旨は、食べ方によって味わいが変わる、とても繊細な納豆です。
ぜひ、ひとつの儀式のように、ゆっくりと味わってみてください。

① 冷蔵庫から出して30分、常温に戻す。
納豆菌が再び動き出し、香りと旨味がふくらみます。

② まずは、何もつけずに2粒。
丹波黒の甘み、香り、発酵によるコク。一粒発酵ならではの輪郭のはっきりした旨味が、最もよくわかる瞬間です。

③ 次に、利き手と逆の手で塩をひとつまみ、20cm上から。
高い位置からふわりと落とすことで、塩が均一に広がり、丹波黒の甘みと塩のミネラルが美しく重なります。

④ 最後は、ごはんと一緒に。
ごはん一口分に対して、極旨を2粒。これが「至福の黄金比」です。
岩塩やオリーブオイル、チーズやワインとの相性も抜群。
和と洋の境界を軽々と越えていくのも、極旨ならではの楽しみ方です。
まずはそのまま。次に塩を少しだけ。極旨のための、たったひとつの作法です。
「納豆屋には絶対にならない」と言った少年が、生涯最高の納豆に辿りつくまで。

大切な方への贈り物に。自分へのご褒美に。25粒の物語を、どうぞご堪能ください。
子どものころ、納豆が大嫌いだった少年が、
今、こうして「納豆の旨味の最高峰」を語っている——。
人生とは、不思議なものです。
納豆は、ただの発酵食品ではありません。
大豆をつくる人、その大豆を預かる納豆屋、そして食べる人。
そのすべてをつなぐ、温かい食文化だと私は思っています。
この極旨 丹波黒豆納豆・一粒発酵は、
私がこれまで積み重ねてきた経験と、失敗と、執念と、感謝のすべてを注ぎ込んだ一皿です。
もしあなたが、
「人生で一度は、本当にとびきりの納豆を味わってみたい」
そう思ってくださるなら——。
この25粒は、きっとその願いに応えてくれると信じています。
一粒一粒を、大切な人の顔を思い浮かべながら、ゆっくりと味わっていただけたら、これほど嬉しいことはありません。
納豆の究極の旨味を追求してきた、二代目福治郎の逸品。
極旨(きわみ)
丹波黒豆納豆・一粒発酵
納豆の旨味は、どこまで高みへ行けるのか。
その問いに二十数年向き合い続けてきた職人が、ようやく辿り着いた答えです。

納豆の旨味の最高峰を目指して生まれた、二代目福治郎の最高傑作。
二代目福治郎・納豆づくりの原点

馬蹄職人から納豆職人へ、人生をかけた挑戦
昭和三十四年に、初代・福治郎が始めた小さな納豆屋「ふく屋」
「ただ、美味い納豆で喜んでもらいたい」——
その想いだけを胸に、家族の手で続けてきた商いです。
その原点は、今も二代目へ、そして三代目へと受け継がれています。
「納豆屋には絶対になりたくない」——そこから始まった物語

「どうせやるなら、日本一の納豆をつくる。」その決意から物語が始まりました。
私は1966年、秋田の小さな納豆屋の長男として生まれました。
子どものころのあだ名は、皮肉にも「なっとうや」。ところが当の本人は、納豆が大嫌いでした。
匂いも、粘りも、あの独特の存在感も苦手で、
「大きくなったら絶対に納豆屋にはならない」と本気で思っていた少年でした。
高校を卒業すると、憧れの大都会・東京へ。
バブル景気の真っ只中、スーツを着て、ビジネスマンとして一旗あげようと意気込んでいました。
ところが、バブルは崩壊。
前を向いて進んでいたはずの道は、突然目の前で途切れてしまいました。
そんなある日、テレビからこんな言葉が耳に飛び込んできます。
「納豆は、科学的に見てもものすごく健康に良い」——。
その瞬間、胸の奥で何かがひっくり返りました。
「納豆屋は、人の健康を支える仕事なんだ」
そう気づいたとき、私は家業を継ぐ決意を固めたのです。
そして、心の中でそっと誓いました。
「どうせやるなら、日本一の納豆をつくる。」
この一粒発酵 丹波黒豆納豆・極旨(きわみ)は、その誓いの延長線上にあります。
丹波黒——黒豆の王様。その潜在能力と、“皮と実”が教えてくれたこと

丹波黒の「皮」と「実」。その浸透圧の違いを知りつくした者だけが扱える豆です。
究極の納豆をつくるなら、まずは豆から。
そう考えた私は、日本中の大豆を探し歩き、その中で一つの答えに辿りつきます。
それが、黒豆の王様と呼ばれる丹波黒大豆です。
ふっくらと大きく、上品な甘みと香ばしい香り。お正月の煮豆としても知られる特別な豆です。
しかし丹波黒には、大きな「難しさ」もありました。
——皮と実の浸透圧が大きく違う。
皮は水を吸うのが遅く、実は水を吸うのが早い。
そのまま水に漬けてしまうと、実だけが先に膨らみ、皮が耐えきれずに破れてしまいます。
皮が破れるということは、その裂け目から、せっかくの旨味が水の中へ流れ出てしまうということ。
つまり、ただ黒豆を水に漬けて煮るだけでは、「本当の丹波黒の旨味」は引き出せないのです。
そこで私たちは、丹波黒と向き合い続ける中で、
「皮と実の吸水スピードを揃える」独自の水戻しの技術 を磨いていきました。
低温倉庫から出した豆をすぐ水に漬けるのではなく、
じっくり2日間かけて常温に戻してから、ようやく吸水を始める——。
たかが水漬け、されど水漬け。
大切なのは、豆の声を聞き、豆の性格を知ることなのです。
究極の旨味に辿りつくために、必要だったのは“一粒発酵”だった。

ひと粒ひと粒に向き合う、一粒発酵という常識外れの製法。
丹波黒のポテンシャルを最大限に引き出すには、従来の納豆づくりでは届かない——。
私たちは、早い段階でその「限界」に気づいていました。
丹波黒は大粒で、一粒ごとに大きさも、水分量も、皮の厚みも、甘みも違います。
その個性は魅力であり、同時に難しさでもあります。
通常の納豆のように、豆をひとかたまりにして発酵させてしまうと、
発酵の熱と湿度は「全体」に広がり、結果としてそれぞれの豆が持つ“最高の瞬間”が平均化されてしまうのです。
では、どうすれば丹波黒のひと粒ひと粒を「いちばん美味しい状態」に導けるのか。
私たちが出した答えは、シンプルで、そして常識外れなものでした。
——一粒ずつ、別々に発酵させてしまえばいい。
ひと粒ごとの水分、ひと粒ごとの火の通り方、ひと粒ごとの菌の付き方。
これらを、すべて“一粒単位”で整えていく。
圧倒的な手間と時間がかかることはわかっていました。
それでも、「究極の旨味」に辿りつくためには、この道しかないと確信していました。
2年8カ月の失敗。そして見つけた“発酵の黄金点 51.2℃”。

51.2℃という、丹波黒がもっともおいしくなる“発酵の黄金点”。
一粒発酵は、想像していた以上に困難な道でした。
温度を変えれば旨味が死に、湿度を変えれば香りが消える。
工場に泊まり込み、何十回、何百回と試作を繰り返しました。
その間にできあがったのは、納豆になりきれない黒豆や、香りの弱い失敗作ばかり。
同業者からは笑われました。
「そんなもの、無理に決まっている」
「そこまでして納豆を作る意味があるのか」
それでも諦めませんでした。
いつか必ず、「これだ」と言える一粒に出会えると信じていたからです。
そしてある日、ついにその瞬間が訪れます。
丹波黒ならではの甘みと香ばしさ、納豆らしい発酵の香り、なめらかな舌ざわり。
すべてが高い次元で調和した、一粒。
そのときの発酵温度が、51.2℃でした。
10時間かけて51.2℃まで上げ、そこから1時間だけ、その状態を保つ。
それ以上でも、それ以下でもダメ。
この「51.2℃で1時間キープ」という一点だけが、丹波黒の旨味を最高に引き出す黄金点だったのです。
こうして、極旨(きわみ) 丹波黒豆納豆・一粒発酵は、ようやく完成しました。
25粒、わずか3%の特大丹波黒だけ——極旨にふさわしい豆とは。

たった25粒。丹波黒の中の、さらに3%だけがここに並びます。
極旨で使用するのは、丹波黒大豆の中でも、さらに厳選されたごく一部の特大粒です。
摘心栽培で育てられた丹波黒大豆の中から、
粒の大きさ、形、表面の状態、色ツヤを一粒ずつ確認し、
わずか3%ほどの5ミリ以上の特大サイズだけを選び抜きます。
熱々の煮豆が冷めないうちに、隣同士で擦れないようにひと粒ずつ納豆菌を付着させ、
さらにそこから特大粒だけを拾い上げ、25マスの升形容器にひと粒ずつ静かに乗せていく——。
煮豆の温度が落ちてしまう前に行わなければならないため、
一度に作れるのは10個が限界です。
こうして選び抜かれた25粒は、まさに丹波黒の「代表選手」。
丹波黒のポテンシャルを、一皿の中に凝縮した姿が、この極旨なのです。
極旨を味わい尽くす、たったひとつの食べ方。
極旨は、食べ方によって味わいが変わる、とても繊細な納豆です。
ぜひ、ひとつの儀式のように、ゆっくりと味わってみてください。

① 冷蔵庫から出して30分、常温に戻す。
納豆菌が再び動き出し、香りと旨味がふくらみます。

② まずは、何もつけずに2粒。
丹波黒の甘み、香り、発酵によるコク。一粒発酵ならではの輪郭のはっきりした旨味が、最もよくわかる瞬間です。

③ 次に、利き手と逆の手で塩をひとつまみ、20cm上から。
高い位置からふわりと落とすことで、塩が均一に広がり、丹波黒の甘みと塩のミネラルが美しく重なります。

④ 最後は、ごはんと一緒に。
ごはん一口分に対して、極旨を2粒。これが「至福の黄金比」です。
岩塩やオリーブオイル、チーズやワインとの相性も抜群。
和と洋の境界を軽々と越えていくのも、極旨ならではの楽しみ方です。
まずはそのまま。次に塩を少しだけ。極旨のための、たったひとつの作法です。
「納豆屋には絶対にならない」と言った少年が、生涯最高の納豆に辿りつくまで。

大切な方への贈り物に。自分へのご褒美に。25粒の物語を、どうぞご堪能ください。
子どものころ、納豆が大嫌いだった少年が、
今、こうして「納豆の旨味の最高峰」を語っている——。
人生とは、不思議なものです。
納豆は、ただの発酵食品ではありません。
大豆をつくる人、その大豆を預かる納豆屋、そして食べる人。
そのすべてをつなぐ、温かい食文化だと私は思っています。
この極旨 丹波黒豆納豆・一粒発酵は、
私がこれまで積み重ねてきた経験と、失敗と、執念と、感謝のすべてを注ぎ込んだ一皿です。
もしあなたが、
「人生で一度は、本当にとびきりの納豆を味わってみたい」
そう思ってくださるなら——。
この25粒は、きっとその願いに応えてくれると信じています。
一粒一粒を、大切な人の顔を思い浮かべながら、ゆっくりと味わっていただけたら、これほど嬉しいことはありません。